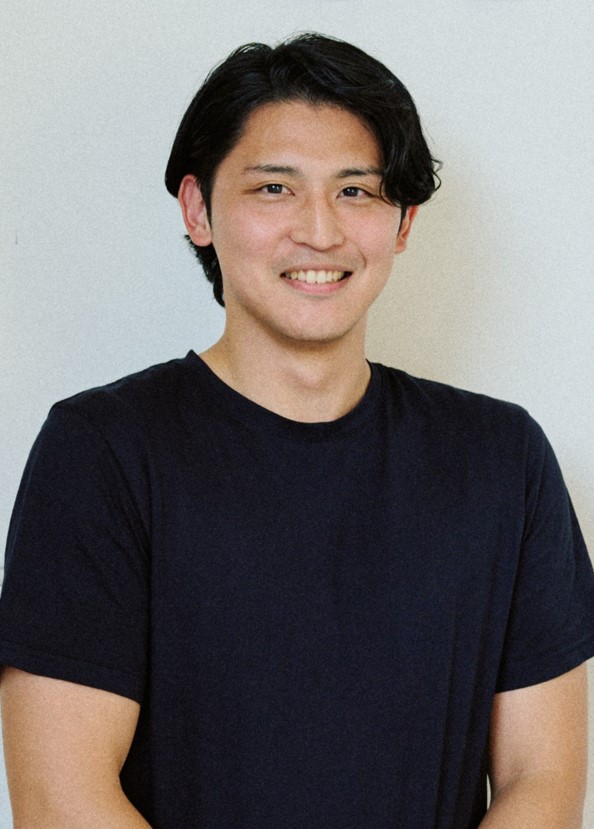CASE STUDY
事例紹介

オフィスカジュアルにおける冬の着膨れや仕事と仕事後のプライベートの両立という、多くの働く女性が抱えている悩み。レディースブランド『23区』を手がける株式会社オンワード樫山は、それらの悩みを解決する新しいオフィスカジュアルを「遊勤コーデ」という新たな概念として提案しました。この新しい概念を、PRとデジタルマーケティングを掛け合わせた「DRメソッド(※)」により市場に届け、2024年秋冬シーズンの本施策実施期間における対象品番の売上、ブランドの新規購入者数の昨対大幅伸長に加え、組織変革の兆しも生まれるなど多くの成果につながりました。株式会社オンワードデジタルラボ デジタルマーケティング部 マネージャー小泉 雄也氏と株式会社オプト プラットフォームサクセス本部 プランニング統括室 兼 コミュニケーションデザイン部 部長の中村 駿介がキャンペーン成功の秘訣を語ります。
※DRメソッドは神谷製作所が開発したPRとデジタル広告を掛け合わせた新マーケティング手法です。オプトと提携し、デジタル面でさらに進化した手法をクライアントに提供しています。
人々の言語化できていない課題を抽出して、解決策を提示
――オンワード樫山とオンワードデジタルラボが抱えていたマーケティング上の課題を教えてください。
小泉氏:まず、オンワード樫山が手がける23区ブランドには、ブランドの売上と新規顧客数の拡大というKPIがあります。ブランドとして毎シーズンのプロモーションを実施していましたが、全体的な設計は毎回不変のため新しいチャレンジの必要性を感じていました。また、定番商品のダウンコートは、私たちの会員プログラム「オンワードメンバーズ」において、新規会員の購入額が全社1位の実績がある商品です。しかし、これまでの訴求はアウター特集といった既存顧客向けのものが中心で、ダウンコート単品で新規顧客に広くアピールする戦略的な訴求ができていませんでした。
一方、私の所属するオンワードデジタルラボは、オンワードメンバーズの会員数の増加と会員売上を伸ばすことをKPIとしています。これまでは、「会員売上=EC売上」として活動していましたが、「会員売上=EC+店舗売上」と、チャネルを問わない売上目標へと変化したことで、新しい施策が求められていました。
――今回、パートナーとしてオプトを選定した理由はどこにありますか?
小泉氏:オプトと神谷製作所さんが開発したDRメソッドは、PRの持つ拡散力とデジタルの持つ強み、具体的にはターゲティングの精度の高さや計測技術の活用などの特性を組み合わせており、大きな可能性を感じました。PRで広い情報拡散をしつつ、デジタルの緻密なターゲティングを掛け合わせて、潜在層へのアプローチはもちろん、顕在層の掘り起こしも期待できる。 一過性の情報拡散で留まりがちなPRの弱みを、デジタルで補完する設計が優れていると思います。
これまで私たちは主にデジタルに関するノウハウを自社ECサイトを中心にグループ内の様々な事業に提供してきました が、DRメソッドの実施により、「脱・デジタル一辺倒」につながる可能性を感じました。私たちとしてはブランドのマーケティングに対しても、デジタルに閉じずに施策の上流から関わりたいと考えていますし、それができるケイパビリティを持つチームだと思っています。
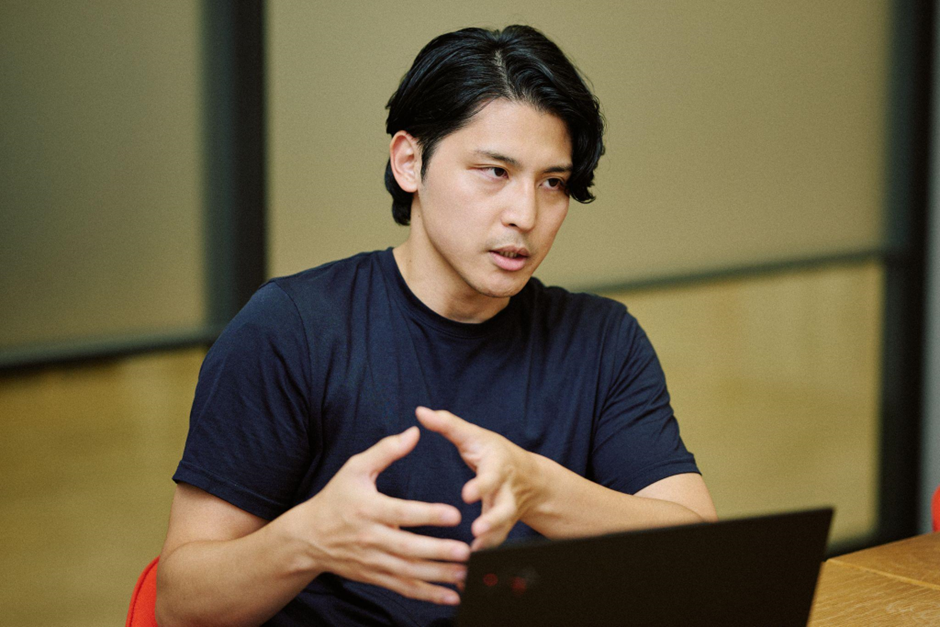
――DRメソッドの詳細を教えてください。
中村:まず、DRとは「デジタル」と「PR」を組み合わせた造語です。広告のコミュニケーションは基本的に「商品やブランドが人々のどのような悩みを解決するのか、どのような魅力を持っているのか」を伝えるフェーズから始まることが多いです。一方で、DRメソッドはその手前にある「あなたにはこのような課題、悩みがありますよね」という需要を喚起する「ペインワード」の設定と、その解決策である「ソリューションワード」を設定するところからコミュニケーションが始まります。現状の課題や悩みに気づいていない、もしくは言語化できてないターゲットに対して、同ブランドの商品を解決策として訴求するためのコミュニケーションを構築しました。
「遊勤コーデ」が冬のオフィスカジュアルの悩みを解決
――今回実施したキャンペーンの全体感について教えてください。どういった欲求を喚起して、どういった解決策を提案したのか。
中村:今回は、冬の定番商品である洗えるダウンの「シレータフタダウン」と、豊富なカラバリで柔らかな着心地の「カシミヤブレンドニット」が訴求対象でした。ダウンは新規会員、ニットは既存会員からの人気が高いので、双方の顧客層へアプローチする狙いがありました。まず、ターゲットを30代有職者の女性に定め、冬服とオフィスカジュアルの悩みに着目しました。冬服の最も大きな悩みとして着膨れがあります。さらに仕事後に出かける際、オフィスカジュアルをファストファッションでそろえると他人とコーディネートが被ってしまったり、プライベートな予定を意識した格好で通勤をすると「 気合い入ってるね」などといわれてしまう。そこから「着膨れ通勤」というペインワードを生み出し、通勤でもプライベートでも活用できる23区のアイテムを訴求する「美シルエットの『遊勤コーデ』」というソリューションワードを考案しました。
小泉氏:今の時代、モノとして圧倒的に差別化できる商品はなかなか生み出せません。ただ、今回のように定番商品もディテールを見ていくと、顧客に伝え切れてない魅力がたくさんあることに気づきました。圧倒的な差別化は難しくても、23区が30年以上かけて培ってきたブランド資産による情緒的価値に加え、今まで伝え切れていなかった機能的な価値を整理して訴求すること で、まだまだお客さまに選んでいただけるという実感を得られました。
中村:次に「遊勤コーデ」というキーワードを広くPRするべく、時勢を捉える狙いで、オリンピック選手の方々をモデルとして起用しました。柔道家の角田夏実選手、元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん、元新体操日本代表の畠山愛理さん、元スピードスケート選手の髙木菜那さんら4名をモデルに起用した広告を展開しました。それぞれ体型の異なるアスリートの皆さんが23区の商品を着ることで、スタイリッシュな冬服コーデが可能になる。メディアを招いたPRイベントでは皆さんにモデルとしてランウェイを歩いていただいた結果、パリオリンピック直後だったこともあり大きな注目を集めました。
――最初に「着膨れ通勤」というペインワードを設定したとのことですが、このペインワードの見つけ方についてオプト流のメソッドがあれば教えてください。
中村:私たちが情報ソースとして重視しているのは、主に、①メディアが盛んに取り上げる事象、②SNS上のソーシャルボイス、③検索キーワードの3点です。購入につながるであろう最終的なキーワードと、その関連キーワードから文脈を読み解きます。どちらかというとワードそのものより、消費者のインサイトがどこにあるのか探ることを大切にしています。これは、人間の持つ潜在的な欲求や感情を深く理解するためには欠かせない視点です。
その背景には、人が意識し、検索できるまでに言語化されている悩みはわずか5パーセント程度に過ぎず、残りの95パーセントはまだ言葉になっていない潜在的なニーズである、という考え方があります。PRは、この「まだ言葉になっていないニーズ」を掘り起こし、言葉にしていく役割も担うと捉えています。そのため、検索キーワードやソーシャルボイスを丁寧に拾い上げ、インサイトを深く探ることが、今後より一層重要になると考えています。

デジタルに閉じないマーケティング全般を担う組織として
――では、今回のキャンペーンにおける具体的な成果を教えてください。
小泉氏:定量成果では、施策で訴求したダウンコートとニットの売上は、施策対象品番の売上、新規顧客数の昨対伸長率は二桁成長となり、長年販売している定番品にしては大きな伸長をみせました。他商品との比較でも、施策対象品番の方が昨対伸長率は25%程度大きく、プロモーション影響による伸長と評価しています。定性成果では、デジタルラボとしての考え方がアップデートされた点が大きな資産になったと考えています。今回は商品起点で商品単体の売上を伸ばす方法を考えた結果、個々の商品はもちろん23区ブランド全体も、プラットフォームであるECサイト売上、ひいては会員売上にも影響する売上伸長が得られました。従来は、ブランド問わないEC売上向上や、新規会員獲得など、ブランドや商品はあまり意識せずプラットフォームドリブンで施策を展開してきました。しかし今回のようにプロダクトドリブンで取り組んだことで結果的に、会員獲得単価やROIなどプラットフォーム全体で向上を目指すKPIの良化が見られたことは発見でした。 オンワード樫山とオンワードデジタルラボが組織の壁を乗り越え一緒になって取り組み、打ち上げ花火で終わらない成果につながり、これまで以上に23区チームとハイレベルかつ高頻度な情報交換ができるようになりました。
――デジタルラボとしてお客さまに届けたい価値、マーケティング上で重要視していることはどのようなものでしょうか?
小泉氏:「プラットフォーム」「ブランド」「プロダクト」という三層構造で考えると、プラットフォームでの差別化はAmazonや楽天のような経済圏や圧倒的なサービス品質をもつ競合との勝負になるため、簡単ではないと思います。 プラットフォームとして真っ向勝負するよりも、一つの販売チャネルとして活用していく方針が賢明かもしれません。やはり私たちが勝負するのはブランドやプロダクトであり、長い年月かけて価値を築いてきたブランドや定番商品、またリアル店舗や販売スタッフなど、オンワードにしかない資産があります。 それを言語化するのはなかなか難しいのですが、そこに魅力を感じてくださっているお客さまは多くいらっしゃいます。商品をつぶさに見ていくと、例えば23区のダウンコートだったら 細部まで作り込まれていて、丁寧なこだわりがたくさんあるので、そういったポイントを紐解いてお伝えしていく。そのためのマーケティングをこれからも続けていきます。
――今回の成果を踏まえて、今後両社としてどういったことにチャレンジしていきたいですか?
小泉氏:定量的にも定性的にも結果を残せましたが、細かい点を見れば改善点もたくさんあります。それらの明確になった課題を次に活かし、より研ぎ澄まされた施策を実現していきたいですね。今回は二つのチームが組織の壁を乗り越え合同で行った事例になりますが、 お客さまから見ればそれは内部事情であり、あまり関係のない話です。あるべき姿は、「顧客理解を通して、OMOの観点からチャネル関係なく、一人ひとりのLTV向上を図る」という顧客起点の考え方で、各部署が有機的に機能することだと考えますが、全社的には広まっているものの浸透しきってはいないと感じます。これを推進するには、個人と組織両面での改善が必要です。個人単位では、社員一人ひとりのマインドチェンジが必要ですし、それを促すための組織構築や制度設計、予算配分など、組織単位の見直しを図っていくことが求められます。まずは私たちが組織の壁を越えてあらゆる部署と連動することで、あるべき姿に近づく一助になればと思っています。
中村:「遊勤コーデ」というワードは単発のプロモーションで終わるものではなく、ブランドとしての資産になってほしいという思いがあります。どうしても点の成果を求められがちなデジタルマーケティングですが、DRメソッドはそこにPRの手法を取り入れることで、一過性ではない資産となる施策を可能にします。23区ブランドとしても引き続き「遊勤コーデ」というワードを使っていただいてるので、より大きく育てていくために節目節目でご支援ができれば嬉しいですね。なにより今回は数字としての成果だけでなく、デジタルラボ、23区チーム双方の組織変革の一歩になれたことが想定外でした。率直に代理店冥利に尽きると感じていますし、私たちとしても大きな学びになりました。